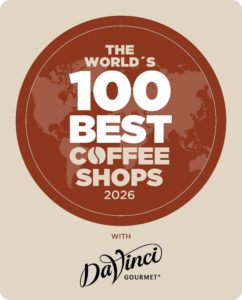全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連)が実施した「第60回学生生活実態調査」によると、ChatGPTに代表される生成AIツールの利用が、全国の大学生の間で急速に広がっていることが明らかになった。2023年10月から11月にかけて実施された本調査では、全国31の国公私立大学に在籍する学部生11,590人から有効回答が寄せられ、生成AIを「常用している」と答えた学生は全体の50.0%に上った。これは、前年度の28.0%から実に22ポイントもの増加となり、生成AIの浸透がこの1年で急加速している実態を示している。
活用シーンはレポートから日常生活まで
生成AIの活用は、単なるレポート作成や要約にとどまらない。学生たちは自由記述の中で、授業や学習の効率化はもちろん、日常生活の中にもAIを取り入れている様子を具体的に語っている。
たとえば、ある文系女子学生は「様々な視点で答えてくれるのが面白い。教育実習での指導案作成時に、仮想の状況をAIに提示して思考のヒントを得る」とし、生成AIを“思考の補助装置”として活用していると述べた。また、文章の添削やメール文の敬語チェックに利用する学生も多く、「企業に送るメールで、正しい敬語かどうか不安な時に役立った」という声も寄せられている。
さらに、初めて学ぶ外国語や数学の自習に生成AIを用いる学生も多い。「言語学習では、例文を入力して全ての単語や文法を解説してもらうのが非常に有効だった」という声や、「数学の分からない部分を尋ねると、考え方を丁寧に教えてくれるので便利だった」という実用的な使い方も見られた。
ネット情報の整理・要約機能に感動したという学生もおり、「ネット上の膨大な情報をまとめてくれるので、効率的に調べ物ができる」と評価する声が多く聞かれた。
一方で不安の声も 「信用しすぎは危険」
便利さの一方で、慎重な姿勢を見せる学生も少なくない。特に、出典不明の情報や誤った内容を生成する「ハルシネーション(幻覚)」の問題については多くの指摘が寄せられている。
ある文系の女子学生は「出所が不明な情報が含まれているので、あくまで参考程度と考え、情報源の確認が不可欠」と述べ、AIに対する過信を戒めている。また、理工系の男子学生からは「専門的な内容では誤りが多く、論文執筆などでは信用できない。ただしPythonのようなプログラミングには一定の有用性がある」といった冷静な評価も見られた。
さらに、「不自然な日本語表現が多い」「そのまま使うと内容が的外れになることがある」といった懸念や、「課題をAIにすべて任せるのは研究倫理に反する」「便利すぎて思考力が衰える」といった倫理的・教育的な問題を指摘する声もあった。
クリエイティブな使い方も続々
注目すべきは、生成AIが“学業のサポート”という枠を超えて、日常生活やクリエイティブな活動にも活用されている点だ。
ある学生は「AIに複数の人格を設定して討論させ、ブレインストーミングの材料にしている」と述べており、AIを対話型の思考ツールとして活用している。さらには「自分の日記を読み込ませて、自分に似た人格のAIを育てている」といったユニークな試みもあった。
他にも、「冷蔵庫の中身から献立を考えてもらう」「具合が悪い時に症状を入力して参考にする」「絵を描いてもらって遊ぶ」「占いやエクササイズの提案に使う」といった実生活への応用が数多く見られ、生成AIが“第二の知恵袋”として多様な場面に溶け込んでいることがうかがえる。
大学教育の在り方そのものが問われる時代へ
全国大学生協連は今回の調査結果について「生成AIの普及は、大学教育の在り方そのものに影響を及ぼす可能性がある」と分析している。学習の個別化・効率化が進む一方で、情報リテラシーや倫理的判断力が今後ますます重要になると指摘。今後も調査を継続し、大学・学生・社会全体がこの変化にどう向き合うかを模索していく必要があるとしている。
調査の詳細は、全国大学生協連の公式サイトにて公開されている。
👉 調査概要・全文はこちら:
https://www.univcoop.or.jp/press/life/report.html